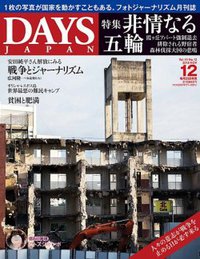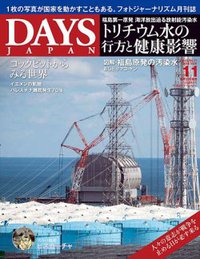2009年04月23日
今帰仁事件
400年前の今日(4/22)、今帰仁城(グスク)が落城しました。
この事件を、「薩摩藩(島津氏)の琉球侵攻」と呼んでいます。
では400年前の今日(旧暦の3月25日)、具体的に何があったのか?
地元今帰仁村でそれを解明する文化講演会がありました。


1609年は沖縄の歴史において、大きな転換期となったことはすでによく知られています。
1609年、旧暦の3月25日(つまり新暦の今日)、現在の今帰仁村にある運天港(当時、琉球王国屈指の良港)に到着した薩摩軍(80艘の船団、およそ3000人)は、翌々日27日に今帰仁城で交戦し、監守一族(琉球王府から北部の統治を任された役人=国王の直系)の居城として城を構えていた今帰仁城を焼き討ちにしました。
この薩摩侵攻(史実に基づけば、薩摩侵略と言うべき)が、のちの今帰仁、もっと言えば琉球社会に及ぼした影響は計り知れないものがありました。
この事件をきっかけに、独自の民族・文化を持っていた独立国としての「琉球王国」は、異民族の支配(もちろん初めての経験)を受けることになったのです。
そしてこの琉球(現在の沖縄)の異民族支配は、実は今日まで続いているわけです(ぜひ明治初期の「琉球処分」を検索してみてください)。
つまり1609年以降の琉球王国の民は、一つは琉球王府、いま一つは薩摩藩という二重支配を受けていたことになります。
翌年の1610年にはかつてなかった大規模な「検地」(納税のための土地測量)が行われています。翌1611年には新たな納税制度が始まっています。
この影響(重い年貢)をもろに受けたのが、首里王府の周辺地域、つまり現在の「やんばる(沖縄本島北部地域)」であり、宮古島や八重山諸島(石垣島等)だったのです。
このように琉球社会に起こった大激震が薩摩の琉球侵攻であり、琉球史においてはこの1609年が、中世と近世を分かつ分水嶺だったことが読み取れます。
最後に、今日の沖縄県を取り巻く状況でいうならば、日本国土の0.6%に当たる沖縄県に、在日米軍基地の約75%が集中する沖縄というのは、一つは日本政府、いま一つは米国政府という二重支配の下にあるのではないかと思うのです。
現状に満足していない沖縄の人たちは、その不満をいったいどちらの政府にぶつけたらいいのか。沖縄の言葉で「わじわじ(歯がゆいという意味)」と言いますが、そういう沖縄社会を覆う閉塞感が、実は今日まで400年間変わることなく続いてきたということなのです。
未来志向で考えたとしても、この「わじわじ感」がいつ解消されるのか、21世紀の今日にあっても、そのトンネルの出口は未だに見えていないのです。
この事件を、「薩摩藩(島津氏)の琉球侵攻」と呼んでいます。
では400年前の今日(旧暦の3月25日)、具体的に何があったのか?
地元今帰仁村でそれを解明する文化講演会がありました。
1609年は沖縄の歴史において、大きな転換期となったことはすでによく知られています。
1609年、旧暦の3月25日(つまり新暦の今日)、現在の今帰仁村にある運天港(当時、琉球王国屈指の良港)に到着した薩摩軍(80艘の船団、およそ3000人)は、翌々日27日に今帰仁城で交戦し、監守一族(琉球王府から北部の統治を任された役人=国王の直系)の居城として城を構えていた今帰仁城を焼き討ちにしました。
この薩摩侵攻(史実に基づけば、薩摩侵略と言うべき)が、のちの今帰仁、もっと言えば琉球社会に及ぼした影響は計り知れないものがありました。
この事件をきっかけに、独自の民族・文化を持っていた独立国としての「琉球王国」は、異民族の支配(もちろん初めての経験)を受けることになったのです。
そしてこの琉球(現在の沖縄)の異民族支配は、実は今日まで続いているわけです(ぜひ明治初期の「琉球処分」を検索してみてください)。
つまり1609年以降の琉球王国の民は、一つは琉球王府、いま一つは薩摩藩という二重支配を受けていたことになります。
翌年の1610年にはかつてなかった大規模な「検地」(納税のための土地測量)が行われています。翌1611年には新たな納税制度が始まっています。
この影響(重い年貢)をもろに受けたのが、首里王府の周辺地域、つまり現在の「やんばる(沖縄本島北部地域)」であり、宮古島や八重山諸島(石垣島等)だったのです。
このように琉球社会に起こった大激震が薩摩の琉球侵攻であり、琉球史においてはこの1609年が、中世と近世を分かつ分水嶺だったことが読み取れます。
最後に、今日の沖縄県を取り巻く状況でいうならば、日本国土の0.6%に当たる沖縄県に、在日米軍基地の約75%が集中する沖縄というのは、一つは日本政府、いま一つは米国政府という二重支配の下にあるのではないかと思うのです。
現状に満足していない沖縄の人たちは、その不満をいったいどちらの政府にぶつけたらいいのか。沖縄の言葉で「わじわじ(歯がゆいという意味)」と言いますが、そういう沖縄社会を覆う閉塞感が、実は今日まで400年間変わることなく続いてきたということなのです。
未来志向で考えたとしても、この「わじわじ感」がいつ解消されるのか、21世紀の今日にあっても、そのトンネルの出口は未だに見えていないのです。
Posted by ミチさん at 00:57│Comments(0)
│琉球・沖縄史