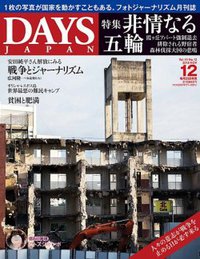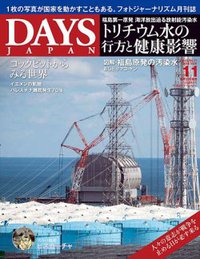2019年03月13日
<乗松聡子の眼> 天皇のタブー視 民主主義と両立しない
<乗松聡子の眼〈15〉> 天皇のタブー視 民主主義と両立しない
今の日本を見ていると、メディアを含む社会全体での「天皇タブー視」が根強いことがわかる。皇室の人については特別な敬語を使用して区別する。天皇皇后についてはやる事なす事、有り難がる報道ばかりで、批判は一切許されない雰囲気がある。外国の客相手には、握手するなど、普通の人間同士として接するのに、相手が日本人の場合はそれが許されないような二重基準がある。主権者の市民に会うときも、「一般参賀」のように高い所から手を振っている。
「陛下」という愛称も、「陛」という字が「宮殿の階段」を意味し、身分の上下を強調した言い方であるが、それが問題視されることはない。日本国憲法で保障される「法の下の平等」は度外視した扱いのように見える。「男女平等」も、男系の世襲を定めている皇室では例外であり、この制度が日本の女性の自尊心に与えている負の影響は測りしれないと思っている。
これらの、大日本帝国憲法下の日本と変わらぬような神聖視およびタブー化は、戦後憲法の主権在民の精神に反している。実際、明仁・美智子夫妻が行く先々にはその「タブーの空気」のようなものが一緒について回り、その周りでは異論が許されなくなる。政府はこの傾向を最大限に利用しているように見える。
今回、夫婦の最後の沖縄訪問ということだが、3月27,28日というタイミングは、象徴的にも実利的にも政府に都合の良いものであった。27日は、1879年の「琉球処分」=天皇を中心とする日本国家に琉球が強制併合された139周年であった。1945年、「皇国」を守るために沖縄が犠牲にされた沖縄戦が慶良間諸島で始まり、天皇の名の下に多くの住民が集団死を強要された時期とも重なった。
これ自他が残酷なことであったが、それに加え、今政府が推し進めている現代の日本軍=自衛隊の役割強化と、南西諸島への配備が加速する中での来沖であった。27日には、全国の陸自部隊の指揮統制を一本化する「陸上総隊」を新設、「島嶼防衛」のための「水陸機動団」が発足した。28日、与那国訪問の日は、小さな島の住民を分断した陸自配備の2周年の日であった。日本の最西端、つまり台湾や中国に手が届きそうな場所にまで「天皇のタブー」の空気を包み込むことによって、沖縄戦以来の琉球弧全体の要塞化を丸ごと飲み込ませるという目論見があったのではないか。
明仁・美智子夫妻については、「平和への想い」や「沖縄を思う気持ち」が「本物」であるといった称賛の声が多く聞こえるが、天皇個人の人柄ばかり注目することで、制度自体の問題に向き合うことを避け、タブーを強化してはいないか。何よりも、天皇が「本物」かどうかよりも、天皇に向き合う自分たちが「主権者」として「本物」なのかを問うべきではないか。政府による「天皇タブー」のりようにかんたんにのせられてしまうのではなく、誰の下でもないうえでもない個人として自由で主体的な思考や意見表明をしているのか、ということである。
天皇タブー視と民主主義は両立できない。タブーは打ち破らないといけない。(琉球新報2018.4.4掲載)
乗松聡子 (「アジア太平洋ジャーナル・ジャパンフォーカス」エディター)
今の日本を見ていると、メディアを含む社会全体での「天皇タブー視」が根強いことがわかる。皇室の人については特別な敬語を使用して区別する。天皇皇后についてはやる事なす事、有り難がる報道ばかりで、批判は一切許されない雰囲気がある。外国の客相手には、握手するなど、普通の人間同士として接するのに、相手が日本人の場合はそれが許されないような二重基準がある。主権者の市民に会うときも、「一般参賀」のように高い所から手を振っている。
「陛下」という愛称も、「陛」という字が「宮殿の階段」を意味し、身分の上下を強調した言い方であるが、それが問題視されることはない。日本国憲法で保障される「法の下の平等」は度外視した扱いのように見える。「男女平等」も、男系の世襲を定めている皇室では例外であり、この制度が日本の女性の自尊心に与えている負の影響は測りしれないと思っている。
これらの、大日本帝国憲法下の日本と変わらぬような神聖視およびタブー化は、戦後憲法の主権在民の精神に反している。実際、明仁・美智子夫妻が行く先々にはその「タブーの空気」のようなものが一緒について回り、その周りでは異論が許されなくなる。政府はこの傾向を最大限に利用しているように見える。
今回、夫婦の最後の沖縄訪問ということだが、3月27,28日というタイミングは、象徴的にも実利的にも政府に都合の良いものであった。27日は、1879年の「琉球処分」=天皇を中心とする日本国家に琉球が強制併合された139周年であった。1945年、「皇国」を守るために沖縄が犠牲にされた沖縄戦が慶良間諸島で始まり、天皇の名の下に多くの住民が集団死を強要された時期とも重なった。
これ自他が残酷なことであったが、それに加え、今政府が推し進めている現代の日本軍=自衛隊の役割強化と、南西諸島への配備が加速する中での来沖であった。27日には、全国の陸自部隊の指揮統制を一本化する「陸上総隊」を新設、「島嶼防衛」のための「水陸機動団」が発足した。28日、与那国訪問の日は、小さな島の住民を分断した陸自配備の2周年の日であった。日本の最西端、つまり台湾や中国に手が届きそうな場所にまで「天皇のタブー」の空気を包み込むことによって、沖縄戦以来の琉球弧全体の要塞化を丸ごと飲み込ませるという目論見があったのではないか。
明仁・美智子夫妻については、「平和への想い」や「沖縄を思う気持ち」が「本物」であるといった称賛の声が多く聞こえるが、天皇個人の人柄ばかり注目することで、制度自体の問題に向き合うことを避け、タブーを強化してはいないか。何よりも、天皇が「本物」かどうかよりも、天皇に向き合う自分たちが「主権者」として「本物」なのかを問うべきではないか。政府による「天皇タブー」のりようにかんたんにのせられてしまうのではなく、誰の下でもないうえでもない個人として自由で主体的な思考や意見表明をしているのか、ということである。
天皇タブー視と民主主義は両立できない。タブーは打ち破らないといけない。(琉球新報2018.4.4掲載)